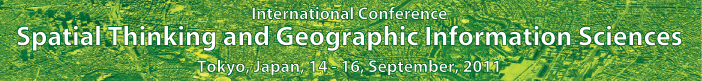2011年9月15日 13:30-14:30
「空間リテラシーを育てる」
サラ・ベドナーズ カレン・ケンプ
2006年、マイケル・グッドチャイルドが、空間リテラシーを「地図の形で、知識をとらえ、やりとりし、上空から見た世界を理解し、認識し、パターンを認識し、読み取り、地理を単なる地表面上の場所一覧ではなく、それ以上のものであると知り、情報を整理し、発見し、縮尺と空間的resolution 解像度といった基本概念を理解するための基礎として地理の価値を認める能力」と説明しました。これは、空間的思考としてざっくりと分類された、幅広いものの見方、知識、技能、感じ方や傾向を含んでいます。また、これはグッドチャイルドによって説明された空間的技能のとても一般的なレベルから地理空間分析の高度なトレーニングを受けるような専門的知識や技能に至るまで、一連の能力の範囲も含まれます。空間的推論は、問題解決や意思決定のために物事を空間的に考える中で使われるプロセスとしてさらに区別できるかもしれません。空間リテラシーは、空間的思考と空間的推論の所産です。もし、人が空間で、空間とともに、空間について考え、判断できれば、その人の空間リテラシーへの取り組みも考えられるからです。
このセッションでは、空間リテラシーの特徴、本質とその発展を反映させたダウンズ (Downs 1994)のモデルに従って話をすすめていきます。そして、いくつかの質問の答えを考えていきます。その質問とは、「空間的思考とは、一連の技能からどのように特徴づけられるか」「空間的思考や空間的推論の専門的技能はどう育成すればよいか」「空間リテラシーとはどう測定でき、評価が可能か」「わたしたちは空間リテラシーを、社会や研究、教育においてどのように育てていけるのか」です。空間リテラシーに必要な教育的基盤と、すべての教育レベルにおける地理学やその他科学の教育者たちが明確に空間的概念、空間的表現の利用と空間的推論の過程を生徒たちに教えられる方法に焦点を当てて、今後について考えるきっかけになるといいと思っています。また、職場での空間的思考の必要性と、教育者たちが、専門家たちの空間的能力の向上のためにどう支援できるかについて考えます。最後に、ここで発表するアイデアをどう実践に移していけばよいか話し合ってきます。
- 参考文献
- Downs, R. (1994)Being and Becoming a Geographer: An Agenda for Geography Education. Annals of the Association of American Geographers, 84(2):175-191.
- Goodchild, M. (2006). The fourth R? Rethinking GIS education. ArcNews, 28(3):5-7.
- スピーカー
- サラ・ベドナーズ(Sarah Bednarz)
- テキサスA&M大学教授、ジオサイエンス学部副学長。現在、地理科学教育研究委員会(GSERC)委員長を務めている。
- カレン・ケンプ(Karen Kemp)
- 南カリフォルニア大学教授(空間科学)。同大学のGIS&Tプログラムのオンライン修士課程で教鞭をとる傍ら、現在居住しているハワイにおいて、GISを通じて西洋とハワイの科学を融合させるプロジェクトを行っている。